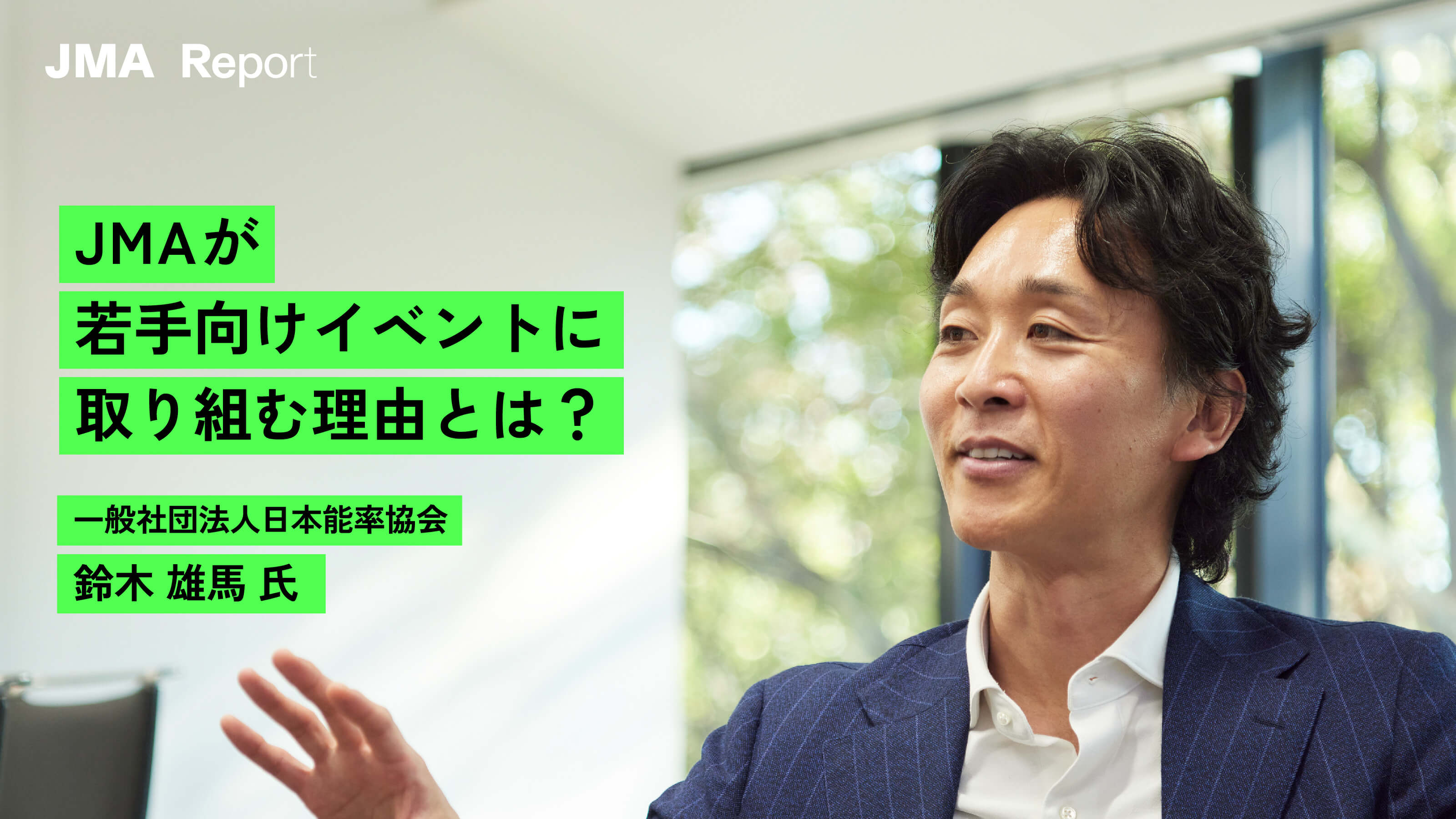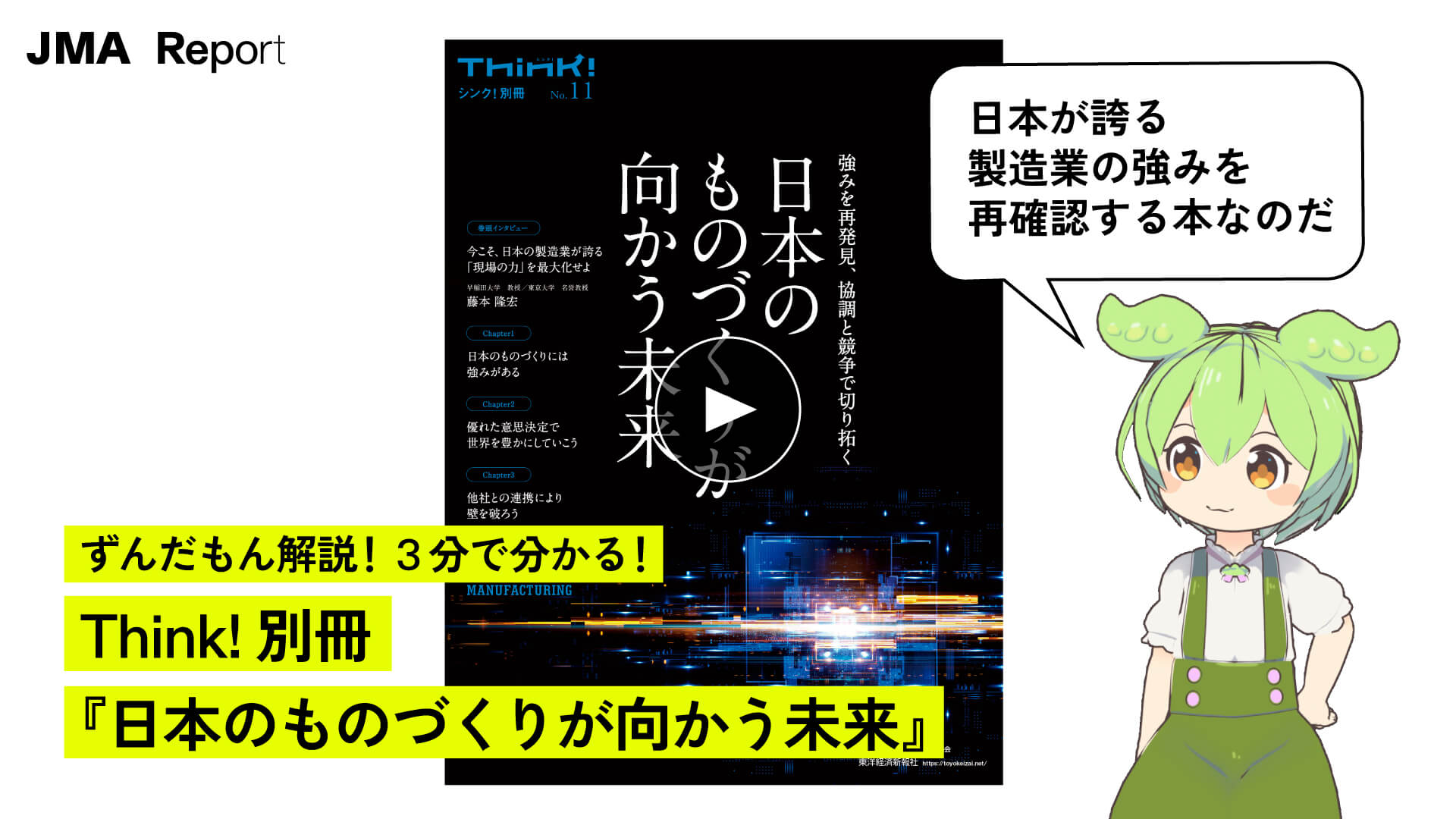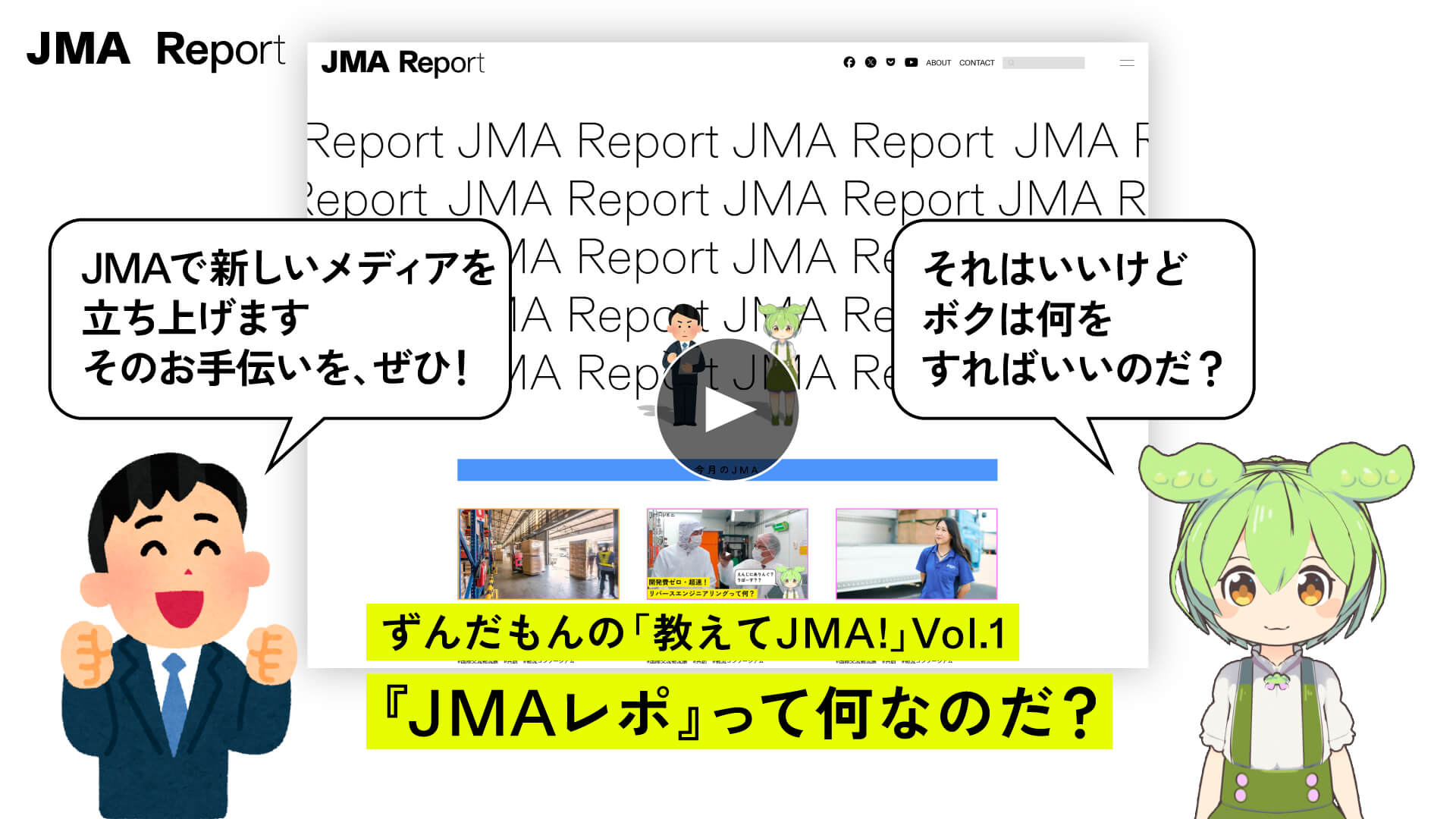JMAは2025年3月3日、「アート思考に触れる『アートが切り拓く経営の未来』」シンポジウムをThe Okura Tokyoで開催しました。本シンポジウムでは国公立5芸術大学(東京藝術大学、愛知県立芸術大学、京都市立芸術大学、金沢美術工芸大学、沖縄県立芸術大学)の学長とソフトバンク特別顧問の宮内謙氏らの協力のもと、2時間にわたって「アートと経営」について話し合いました。
会場には上場企業の経営幹部を中心に70名ほどが集まりました。経営にアートを取り入れるというテーマに寄せられる期待は非常に大きく、JMAではこの分野における知見を集めて、さまざまな形で日本企業の成長の後押しをしていく予定です。
問題提起:なぜ今、経営にアートが必要なのか?
冒頭、JMAの中村正己会長から、「日本企業は従来のサイエンスやクラフトに、アートのもつ文化的創造性も加えることで、成長することができるのではないか。次世代経営者には、アートが持つ創造性を活かした、これまでの概念を超えた新しいアプローチが求められている」と経営とアートの関係についての問題提起がありました。
次に、東京都副知事の宮坂学氏から、「テクノロジーやデザインは課題を解決するためにあるが、そもそも課題は何なのか?と考える必要がある。その点において、アートという側面が重要だ」とアート思考についての期待がありました。また、「東京都はスマートシティ化を進める一方で、単なる利便性だけではなく、アートによる豊かな都市空間の創造も重視している。ニューヨークの高架跡地を再開発した空中庭園『ハイライン』のように、アートを効果的に活用した公共空間づくりは、これからの都市計画において重要な視点だ」と都市計画とアートについても指摘がありました。
パネルディスカッション:アートが持つ力とは何か?
続いて、「経営におけるアート実装の必要性とは」「アートを導入した都市空間の新潮流」のパネルディスカッションへ。ソフトバンク株式会社特別顧問でKアート株式会社代表の宮内謙氏がモデレーターを務め、パネリストとして東京芸術大学学長の日比野克彦氏、京都市立芸術大学学長の赤松玉女氏、愛知県立芸術大学学長の白河宗利氏、株式会社観光企画設計社代表取締役社長の鈴木裕氏、株式会社竹中工務店取締役執行役員副社長の菅順二氏の5名が登壇しました。それぞれの発表の要旨は次のとおり。

東京藝術大学 学長 日比野克彦 氏
「東京芸大では、SDGsの文脈でアートの役割を再定義しようとしている。SDGsの17のゴールには芸術・文化という言葉は含まれていないが、芸術やアートには社会や人が持つ課題をいち早く感覚的に察知する力がある。そして、人々の心を動かす力があると考えている。それらの力こそが、社会課題に立ち向かう原動力だと考えている。現在、41の団体と連携し、『文化的処方』という新しい概念を提案している。これは、文化や芸術との関わりが人々のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を向上させるという考えに基づくもので、効果を実証的に示すため、さまざまな施設と協力しながら研究を進めている。さらに、『こころの産業』という新しいビジネスの創出も目指している。これは文化的手法を持続可能な形で提供するための経営的アプローチだ。これらの取り組みを通じて、次世代のSDGsの実現に貢献したいと考えている」

京都市立芸術大学 学長 赤松玉女 氏
「ビジネスは商品やサービスを通じて商うことが目的であり、あったらいいなという実用的な価値やニーズに応えること。一方、アートは本来表現すること自体が目的であるが、表現の前段の時代への問いかけや社会への問いかけが、時には理解しがたい革新的な価値を生み出すことがある。アートは単なる才能でなく、教育を通じて育成される力だ。京都芸大では、145年の歴史の中で、横断的な教育アプローチを大切にし、創造的な人財を育成している。特に重要なのが、デッサン教育で、これは単に絵を上手く描くためのものではない。世界や社会、自分を観察する力、他者からどう見えるのかという客観視する力、そして、批判に耐え、繰り返し挑戦する持久力を養っている。2023年10月、本学は京都駅近くに移転した。ビジネスの中心に位置するこの立地選択は、京都市が芸術文化を重視する姿勢の表れといえる。新キャンパスでは、学生たちがさまざまな形で作品を展示し、協働しながら成長を続けている」

愛知県立芸術大学 学長 白河宗利 氏
「成功した経営者や発明家(A・アインシュタイン、P・ドラッカー、スティーブ・ジョブズ、ソニーの盛田昭夫氏など)は、美術作品を見るように、世界を俯瞰する/観察する能力を持つ。サイエンス思考は客観的だが時間を要し、クラフト思考は過去の成功例に縛られる傾向がある。一方、アート思考は革新的なアイデアを生み出せるが、マーケットとの乖離が懸念される。だが、彼らはマーケットやトレンドを意識せず、個人の感性や直感を持つことで革新的なサービスやアイデアを生みだした。これからの企業には、この三つの思考のバランスが重要であり、どこかに偏ってはいけない。そして、アートの持つ心を動かす力真の力を理解するには、絵に観て、音に触れ、匂いを感じるなど実際に五感で作品を体験することも肝要だ」

株式会社観光企画設計社 代表取締役社長 鈴木裕 氏
「近年、アートはホテルの壁の一部として取り入れられるようになってきた。ホテルインディゴ犬山有楽町では、国宝犬山城や如庵、木曽川など地域の特徴をアートとして客室に取り入れている。アートを通じたホスピタリティには、従業員満足度の向上や、心身の健康への良い影響が確認されており、WHOでもその効果が報告されている。ウェルビーイングの時代において、アートは万国共通の言語としてだけでなく、新しい価値を生み出す重要な要素となっている」

株式会社竹中工務店 取締役執行役員副社長 菅順二 氏
「我々が建築にアートを取り入れる理由は三つある。一つは、建築空間のコンセプトを アートにより補強すること。次に、利用者のウェルネスを向上させること。そして、若手アーティストなどに作品制作の場を提供し、文化に貢献することだ。2004年竣工の竹中工務店東京本店では、設計完了後の施工初期段階において、アート設置場所を選定し、各場所についてアーティストによるコンペを実施した。主に若手アーティストに依頼し、建物の光の取り入れ方という空間コンセプトに即した作品を制作いただいた。自社ビルでは建設費の約5%をアートに充当しており、顧客の建物においては0.5%程度を目標としている。建築とアートを組み合わせることにより、利用者の感受性を豊かにする空間を創出することが可能だ。それが、間接的にアート思考にもつながっていくと考えている」

ソフトバンク株式会社 特別顧問 / K アート株式会社 代表 宮内 謙 氏
発表のあと、ディスカッションも行われ、モデレーターの宮内氏は、「アートは人と違う想像や新しい発見、つまり0から1を生み出す分野だ。日比野氏の『こころの産業』という概念は、アートが人の心を動かす力を示している。これはマーケティングや商品開発な ど、ビジネスのさまざまな場面で重要で、経営に大きな影響を与える。多くの企業は過去の帰納法的発想に頼りがちだが、アート思考は『あり得ない』ものを見出し、新しいビジネスを生む可能性を秘めている」とアートがビジネスにもたらす効果についてまとめました。
事例紹介1:JMAのオフィス改修プロジェクト
JMA経営・人材革新センター長の富浦渉氏から、JMAのオフィス改修プロジェクトについて紹介されました。富浦氏は「日頃から我々は無意識のうちに『こうあるべきだ』という固定観念に縛られている。しかし、変化を起こすためには、その枠を超える必要がある。論理だけでなく、創造的な発想が企業の競争力を左右していく。「感性×論理=これからの時代に求められるビジネススキル」だと我々は考えている。そこで、今までにはない新しい発想が生まれる環境を目指し、研修室やオフィスの改修をまさに今行っている」と説明。このオフィス改修の監修者であるアートディレクターの土屋純氏は、「2024年7月の打ち合わせで『現状を変えたい』という要望を受け、それをメインコンセプトに据えた。本社周辺の象徴的な東京タワーを新しい視点で捉え直すことをサブコンセプトとした。エントランスには写真家のしんどうあすか氏による東京タワーのアート作品を設置するほか、ラウンジスペース、廊下の壁面、受付カウンター、セミナールーム、1階のセミナールームなどにアートを配置する。この改修により、職員やセミナー受講者に新しい刺激を提供し、感性や創造性を育む場となることを期待している」とオフィス改修の狙いを解説しました。

アートディレクター 土屋 純 氏
事例紹介2:東急ステイ日本橋のリニューアル
アートと経営についての事例紹介の第二弾として、東急リゾーツ&ステイ株式会社ステイ企画統括部シニアマネージャーの上原崇氏とアートディレクターの渡辺明日香氏から東急ステイ日本橋リニューアルについて紹介されました。上原崇氏は「東急ステイ日本橋は 2000年開業の123室のホテルで、今回のリニューアルでは日本文化をより深く体験できる場所を目指した。お客様のニーズはモノからコトへと変化しており、特に外国人観光客は日本の文化体験を求めている」と説明。ディレクター兼デザイナー・アーティストとして携わった渡辺明日香氏は「プロジェクトのテーマは『光と彩りの交差点』。日本橋は五街道の起点であり商業の中心地として、人や物、そして今と昔が行き交う場所という意味を込めた」とリニューアルの狙いを解説しました。

東急リゾーツ&ステイ株式会社 ステイ企画統括部 シニアマネージャー 上原 崇 氏
アートディレクター 渡辺 明日香 氏
事例紹介3:WeWorkにおける場所づくりとアート
アートと経営についての事例紹介の第三弾として、WWJ株式会社代表取締役社長兼CEOのユー・ジョニー・ジョン・ワン氏からWeWorkの空間作りについて紹介されました。ユー・ジョニー・ジョン・ワン氏は「WeWorkでは、人々をインスパイアする環境をデザインしている。その中心にあるのがアートだ。アートを通じて、人々はオープンな気持ちになり、コミュニティが自然と形成されていく。日本全国41カ所の拠点では、それぞれの場所のアイデンティティを表現するため、地域の文化と歴史を深く理解した上でアートを選定している。地元のアーティストとのコラボレーションを重視している。WeWorkにとってアートは単なる装飾ではなく、私たちの存在の中心だ」とWeWorkにおけるアートの重要性を解説しました。

WWJ 株式会社 代表取締役社長 兼 CEO ユー・ジョニー・ジョン・ワン 氏
JMAで構想中のアートを取り入れた経営層向けセミナー
JMAで構想中のアートを取り入れた新しいセミナーについて、JMA経営人材革新センター組織人材開発グループ長の鈴木雄馬氏から発表がありました。鈴木氏は「現在、日本企業は先の見通せない経営環境に直面しており、従来の成功パターンやケーススタディだけでは世界競争に対応することが難しくなってきている。そこでJMAではアートという新しいアプローチに着目し、ビジネスパーソン向けの教育研修にアート思考を取り入れることで、新しい価値創造を目指していく。これまでの研修はおもにクラフトとサイエンスに基づくビジネス教育が中心だったが、今後はアート的要素も重要になると考えている。具体的には、経営層向けの既存研修へのアート要素の導入や、芸術大学と連携したプロラグムなどを構想している。様々なパートナーと連携し、より充実したプログラムを展開していく予定だ」と今後の構想を解説しました。

JMA経営人材革新センター 組織人材開発グループ長 鈴木雄馬 氏
本シンポジウムでは、JMAの取り組みとともに、直感や感性、独創性に基づくアート思考がこれからの経営においていかに重要であるかが深く議論されました。