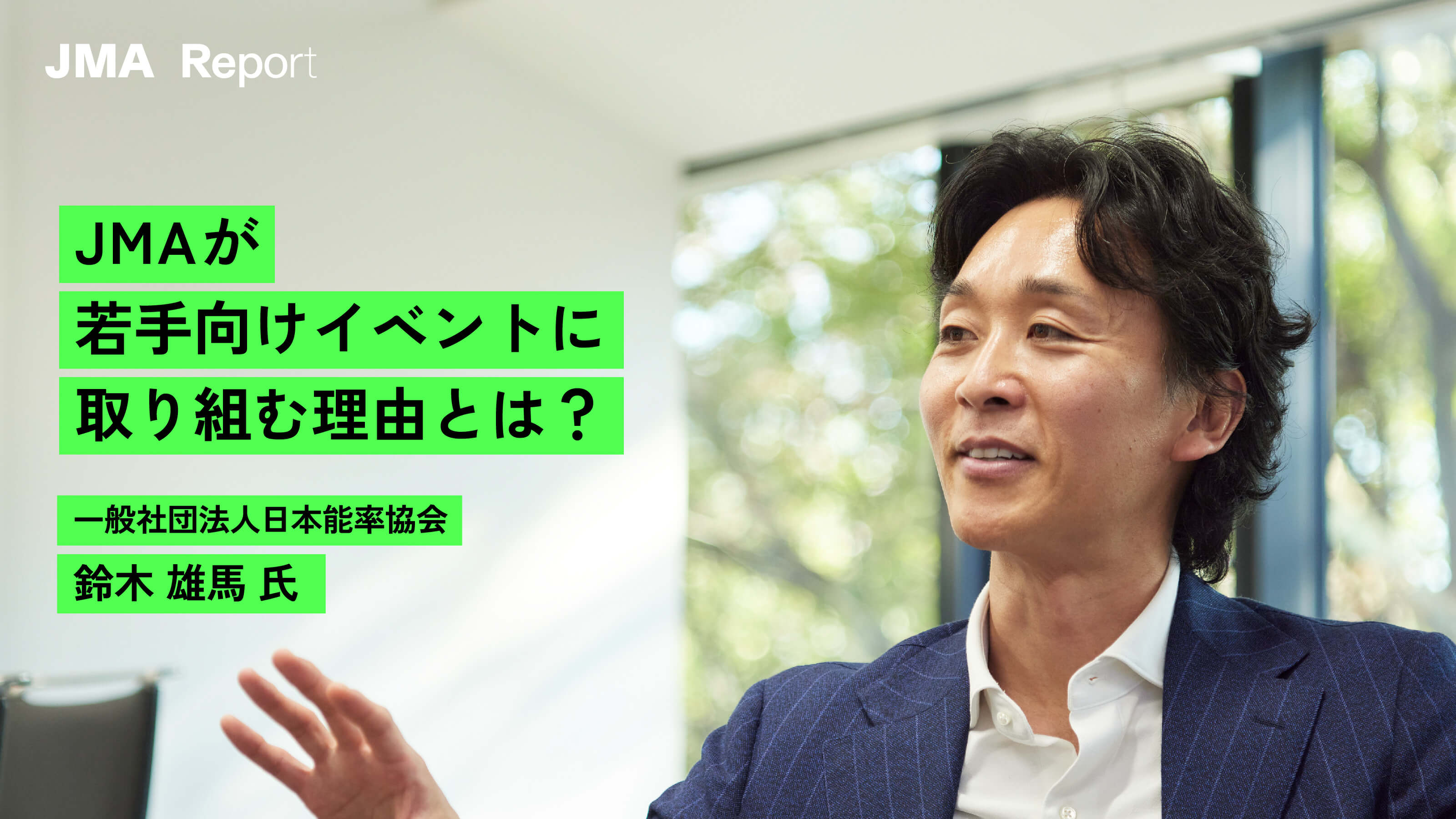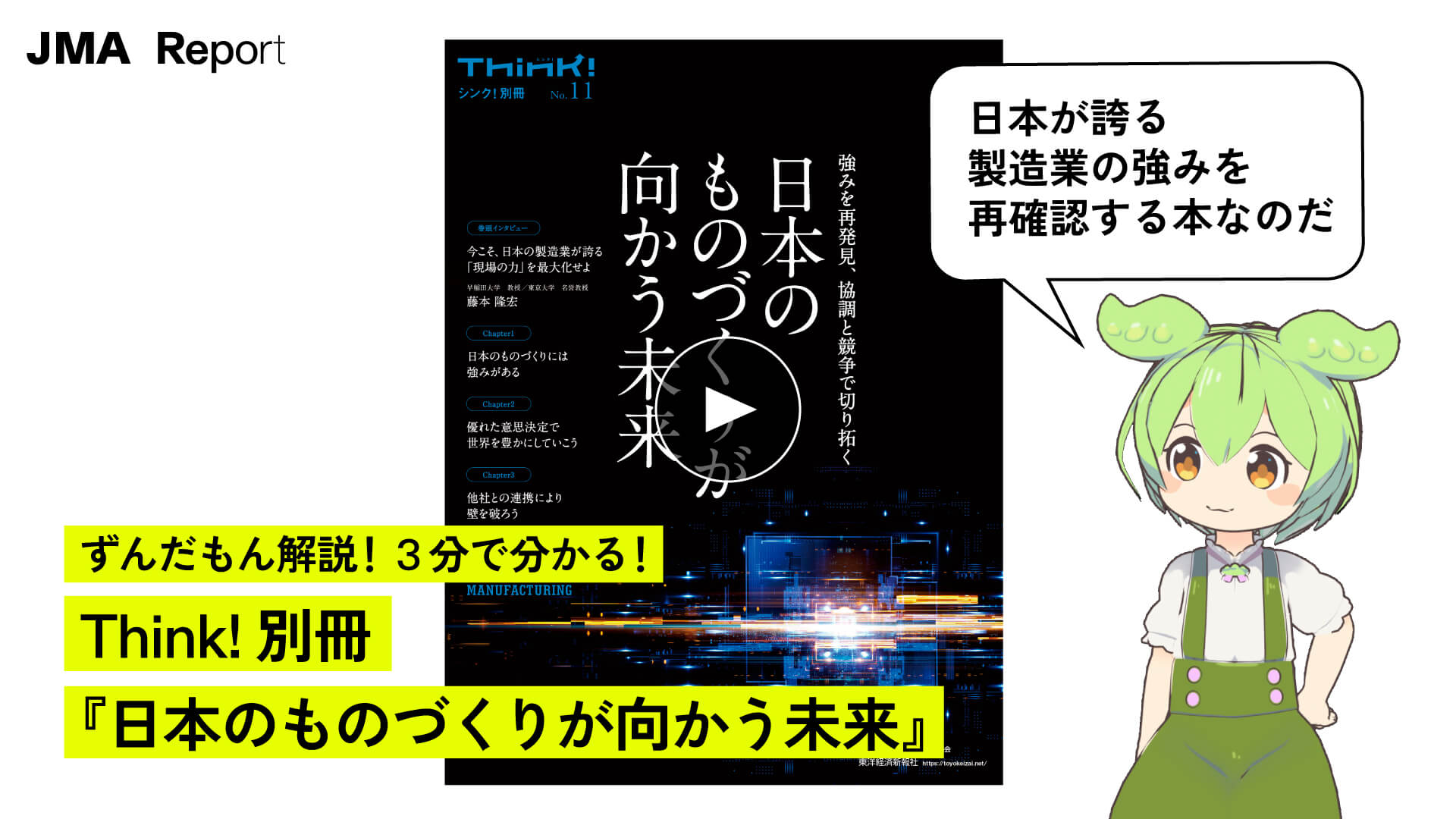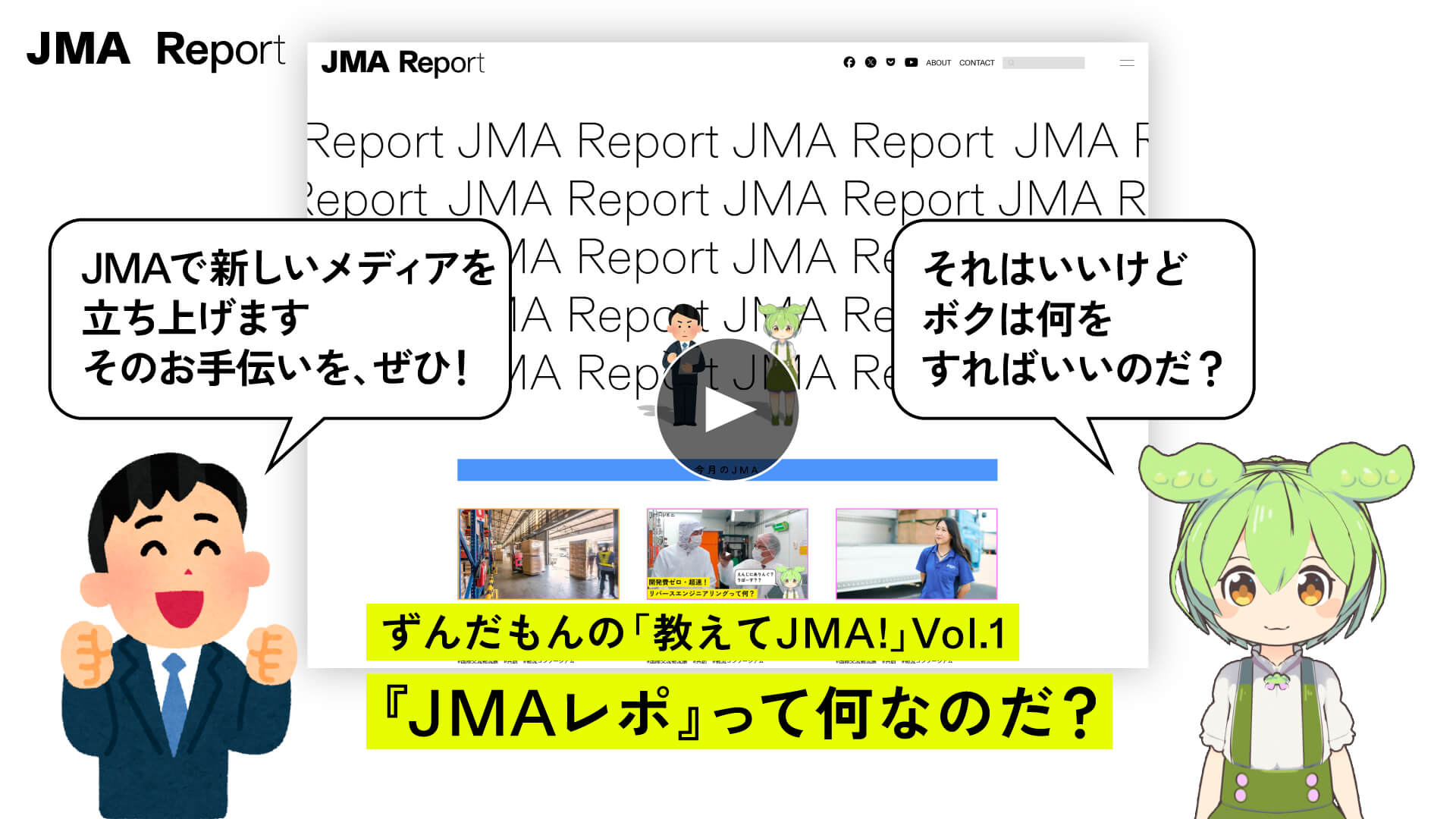ビジネスの世界では「健康経営」の重要性が高まっています。JMA会員限定の「JMAマネジメント講演会プレミアム」は「役員×アスリート×健康経営」がテーマ。アスリートの豊富な経験と知識を共有し、役員が健康経営への理解を深める講演会です。
第2回のゲストは東京ヤクルトスワローズ投手の石川雅規氏です。石川氏をサポートする森永製菓inトレーニングラボの下薗聖真氏、三好友香氏にもご登壇いただき、野球界最年長投手である石川選手の「活躍し続けられる理由」を紐解いていきます(2024年12月23日開催)。
【講演者】
石川雅規氏 東京ヤクルトスワローズ 投手
下薗聖真氏 森永製菓株式会社inトレーニングラボ パフォーマンススペシャリスト
三好友香氏 森永製菓株式会社inトレーニングラボ ニュートリションスペシャリスト
【コーディネーター】
川名浩一氏 日揮ホールディングス株式会社 元代表取締役社長、株式会社レノバ 取締役


第一線で活躍し続ける秘訣とは
川名:石川選手は23年にわたり投手として活躍されています。まず、プロ野球界で長年プレーし続けるために必要な能力やスキルは何でしょうか?
石川:プロ野球は10人が入団したら、10人が辞めていく世界です。その世界で生きていくために、1年目から自分の長所、短所をよく考えました。投手として球が速いわけでも、すごい変化球が投げられるわけでもない。それであれば、けがをせずに、いつでも投げられる存在でいたいと考えました。年間143試合ありますから球団としてはイニングを消化できる「イニングイーター」が必要であり、投球回数が多ければ評価もしてもらえます。いつ声がかかってもよいように、身体のコンディショニングを整えて、常にファイティングポーズを取れる状態でいることは意識してきましたね。
川名:長いキャリアの中で培われた哲学や考え方のルーティンはありますか?
石川:まず、「日々新たなり」です。寝て起きたら新しい1日の始まりです。20代、30代、40代といった年代によっても、その日の気分によっても、見えてくる風景は変わります。1日1日を新鮮な気持ちで楽しむことを心がけています。
僕は、ヤクルトに入団した時に正捕手を務められていた古田敦也さんに「プロ野球を続けるための3つの秘訣」を教わりました。まず「けがをしないこと」です。けがをしては大好きな野球が仕事としてプレーできませんからね。2つ目は「敵をつくらないこと」。不必要に好かれる必要はないけれど、チームメイトや監督、コーチ、スタッフがいるなかで、「敵をつくらず、応援される人になりなさい」と言われました。3つ目は、忘れてしまったんです。先日、古田さんにお聞きしたら「俺も忘れた」とおっしゃっていました(笑)。
川名:石川さんが考える3つ目は何でしょう?
石川:「あきらめないこと」です。僕は今、44歳で、2025年度のシーズンは45歳になります。早生まれですから46歳の年代です。でも、自分で限界を決めず、これから全盛期が来ると信じて、あと14勝を獲得して、200勝を絶対に達成できると信じています。
川名:「信じれば意思は通る」ですね。健康、共感、信念という3つの秘訣は、どれも企業経営に通じます。

【プロフィール】
石川雅規
2001年自由獲得枠でヤクルトスワローズに入団。2002年4月に初登板初勝利と華々しくデビューを飾り、新人ながらローテーションを守り12勝を記録し、新人王を受賞。現在も球界現役最年長選手としてNPB通算186勝、東京ヤクルトスワローズの投手として活躍中。2024年はNPB史上初となるデビューから23年連続勝利を達成。あわせて、23年連続安打を放っており、「投手としてプロ1年目から」および「大卒としてプロ1年目から」としては最長記録を継続中。
負けた悔しさを乗り越えるために
川名:石川選手の言葉と行動からは強い向上心を感じます。いつ頃から芽生え始めたのですか?
石川:僕は1800gの未熟児で生まれて、体もずっと弱くて、中学1年生の時は身長が137cmしかありませんでした。野球を始めて、とにかく野球がうまくなりたい、体の大きな人より試合に出るにはどうしたらよいかをいつも考えていました。野球がうまくなりたい気持ちは今でも色褪せずに持ち続けています。45歳を迎える来年、自分のキャリアで最高の成績を残せると信じています。いつかユニフォームを脱ぐ時が来るかもしれませんが、その先にも次の夢があるはずです。人生の最後まで夢を追い続けるというのが自分の性分に合っていると思いますね。
川名:気持ちの強さを持った石川選手でも、試合で負ける時もあれば、ホームランを打たれる時もあります。つらい時は、どのように乗り越えているのですか?
石川:先発のローテーションに入ると年間25試合から30試合で投げます。思い通りに投げられて勝てる試合は1試合あるか、ないかです。そういう意味では、調子が良くない時にどういうピッチングをするかがとても大切です。
でも、試合に負ければ悔しいし、次への不安もあります。不安な気持ちを乗り越えるために必要なのは「次への準備」です。「これだけやったんだ」という準備の納得感によって不安が和らいでいきます。準備に没頭することで、嫌なこと、しんどいことを忘れることもできます。そして、失敗はくよくよ悩まず、割り切って「次にどう生かすか」を考える。若い頃は引きずることもありましたが、今は生かすことを考えられるようになっています。
川名:試合への準備にも関連しますが、昨今はプロ野球でもデータやテクノロジーが分析やトレーニングに導入されています。石川選手も活用されていますか?
石川:例えばバッターであれば打球の速度や角度が計測できます。その数値が上がれば、ホームランの確率が上がるので、このバッターに対してどの球を投げたら打球速度を抑えられるかは気にしていますね。若手の中には、パフォーマンスの質を効果的に高めるために、多くの情報を取り入れている選手もいます。でも、質を高めるには、量をこなすプロセスが必要です。たくさんのトレーニング量をこなしていなければ、質の良さ悪さは分からない。ですから、僕は昔ながらの走り込みや投げ込みをしっかりやることを大切にしたうえで、データを駆使する方法を選んでいます。いわば身体の感覚とデータの「いいとこ取り」を目指しています。

練習も栄養も “自分ごと” にしなければ意味がない
川名:次のテーマは健康と体力強化ということで、森永製菓inトレーニングラボのお2人にお伺いできればと思います。石川選手はどんな方ですか?
下薗:石川さんは、本当にどこからでも情報収集をしようという意欲がすごいですね。僕は野球経験者ではないのですが、ある時、「握ってみて」とボールを渡されました。僕が何気なく握ってみると、「そういう握り方もありだな」と観察されていました。ラボには他にもプロ野球選手が来ています。基本的には石川さんより若いのですが、どんどん声をかけて「その変化球ってどう投げるの?」とご自分から質問されています。その探究心は本当に素晴らしいですね。
三好:栄養面を担当する私も、石川さんの好奇心には驚かされます。いろいろなところにアンテナを張っていて、「こういう新しい食材の噂を聞いたけど、どうですか」と聞いてくださります。ご自分で情報を仕入れる意欲が他の選手と比べても圧倒的に強いので、オフシーズンに石川選手がいらっしゃる時は、どんな質問をされるか、いつもドキドキしています。
川名:トレーナーの立場から、トレーニングや栄養面でプロのアスリートに気をつけてもらっていることって何でしょうか?
下薗:石川さんは、自分自身で身体と向き合うという基礎が確立されていますが、トップのアスリートでも意外とその意識が持てない方はいます。ですからトレーナーが何かをしてあげるというよりは、アスリート自身が自分で取り組むための意識づけを大切にしています。弊社のラボに来て、なんとなく指示されたプログラムをこなすだけではあまり効果はありません。トレーニングの意味を理解し、それを何につなげるのかを意識するのが大事だと思います。
三好:栄養面も同じですね。ひとり暮らし、寮生活、家族との自宅暮らしなど、選手によって生活環境は異なります。選手自身が栄養指導の意味を理解しなければ、ご自分の環境で取り入れることはできません。それに提案されたメニューであっても、トレーニングの量によって食べる量を調整する必要もあります。それができなければ、期待した回復や体組成にはならないのです。選手自身が栄養について学び、最終的には私の出番がなくなる状態が望ましいと思いながらサポートをしています。出番がないのは少し寂しいですが(笑)。
川名:企業でも社員一人ひとりが仕事の目的を理解し、業務のあり方について考え、時に疑っていきながら最終的には納得して業務に取り組むということが大切です。

【プロフィール】
下薗聖真
森永製菓株式会社inトレーニングラボ パフォーマンススペシャリスト。日本スポーツ協会アスレティックトレーナー、日本コンディショニング協会PCT。国際武道大学大学院でスポーツ医科学修士を取得後、トップアスリートの競技パフォーマンス向上や怪我予防のための包括的なサポートに従事。2013年より現職 。

【プロフィール】
三好友香
森永製菓株式会社inトレーニングラボ ニュートリションスペシャリスト。管理栄養士、スポーツ栄養士、NSCA CSCS。畿央大学健康科学部健康栄養学科を卒業後、スポーツクリニックで術後患者への栄養指導、大学ラグビーチームのサポートを経て、現職。

気軽な声がけでチーム力を高める
川名:石川選手はヤクルト一筋23年で、チームへの強い愛情をお持ちです。ベテランとしてリーダーシップを発揮していると思いますが、どのようなことを心がけていますか?
石川:若い選手とのコミュニケーションでは、とにかく声をかけるようにしています。新人選手と接する際には、その選手の出身校などを調べて、「この人知っている?」など共通の話題を自分で用意するようにしています。同じ時代に、同じユニフォームを着て、共に優勝を目指しているのだから、できるだけ良い環境をつくりたいと考えています。野手では今シーズンで引退した青木宣親選手、投手では僕が最年長だったので、2人でどんどん若い選手に声をかけていましたね。
三好:トレーニングラボでも、石川さんが若い選手にフランクに声をかけている様子をよく目にします。それも、石川さんが周りから信頼され、長い間活躍されている理由ではないかと思います。
石川:若い選手はもちろんですが、トレードで入団した選手、来日した外国人選手とのコミュニケーションも大切にしています。きっと不安でいっぱいだろうけど、「仲間だよ」ってことを分かってほしいし、チームの輪に入ってほしいから、メチャクチャ話に行きますね。食事も大切にしています。一緒にご飯に行ったり、一杯飲むと打ち解けるので。もちろん、お酒を飲まなくて、コーラで乾杯でもOKです。
川名:結果を出せずに悶々としている選手にはどう声をかけますか?
石川:悔しいのは本人が一番分かっているから、とにかく話を聞いて、励まします。
川名:孤独にしない、ということですね。
石川:孤独にはしたくないですね。話をしっかり聞いたうえで、「来年、再来年、5年後、10年後にどうなっていたいかを思いながら、トレーニングをしていこう」と促しています。とにかく、まずは声がけです。「おはよう」「元気?」「昨日のM1見た?」といった気軽な言葉でよいと思います。

終わりなき夢に向かって
川名:石川選手は秋田県の出身で、故郷で野球教室をされていると聞きました。
石川:指導というよりは、とにかく参加する子どもたち全員に声をかけ、コミュニケーションを取るようにしています。僕自身、小学生の頃に「名球会野球教室」が地元で開催されて、金田正一さんや米田哲也さんが来てくれました。その時に、ピッチャーが200人ぐらいいる中で米田さんに「いい投げ方しているから、がんばれよ」とみんなの前で褒めてもらえたんです。そのことがすごく大きかったから、僕も子どもたちと触れ合う時間をつくりたくて、野球教室を開催しています。
川名:米田さんの言葉は、石川選手にとって宝物だったのでしょうね。ご自身は、引退後、指導者の道は考えていますか?
石川:僕はとにかく好奇心が旺盛で、いろんな世界を見てみたいという気持ちが強いです。外の世界を見て、勉強して、その延長線上に監督やコーチというのがあれば、やってみたいと思います。
幼い頃、寝る前に「僕は大きくなったら野球選手になるんだろうな」と思っていました。青木選手も幼稚園生の時に同じように思っていたそうです。
根性論ではないですが、気持ちはとても大切です。「念ずれば花開く」と言いますが、身体の基礎をしっかりと保ちながら現役投手としての目標を追い求め、そこから生まれる新たな夢に向かっていきたいと思います。
川名:ありがとうございました。200勝に向かって活躍されることを応援しています。
石川:ありがとうございました。


【プロフィール】
川名浩一
1982年日揮株式会社(現日揮ホールディングス)入社。インドネシア、イラン、UAE(アブダビ)、英国など15年間海外駐在。2011年〜17年代表取締役社長。2020年6月退社。現在は、株式会社レノバの取締役会長。また、バンダイナムコホールディングス、クボタ、東京エレクトロンデバイス等の社外取締役のほか、プライベートエクイティのKKRジャパンのアドバイザー、Citiグループジャパンのアドバイザリーボード委員を務める。2021年よりルブリスト株式会社の代表取締役としてベンチャー企業経営の支援活動を行う。
【コーディネーターの視点 川名浩一氏】
石川選手が小さな身体でプロ野球を代表する記録を打ち立て、長く第一線で活躍し続けている秘訣は、自分で限界を作らず、常に好奇心と向上心を持って心身を鍛え続けたことと、周囲との良質なコミュニケーション能力にありました。
「質」を高めるには「量」をこなさないと駄目だという持論は、実際にやってきた者だけが言える言葉ですね。
トップアスリートにも、企業の優秀な方にも共通する、自身を客観視できる能力をお持ちで、自分の弱みも理解した上で、強みを極限まで追求して今の姿があるのでしょう。
当日の講演会では、本記事の内容以外にも、優勝する監督やチームに見られる傾向など、経営に役立つエピソードを披露していただきました。また、講演後は懇親会も開催され、石川選手のサイン会や来場者同士での交流が行われました。今後も「JMAマネジメント講演会プレミアム」は続きます。ぜひ、講演会にご来場ください。